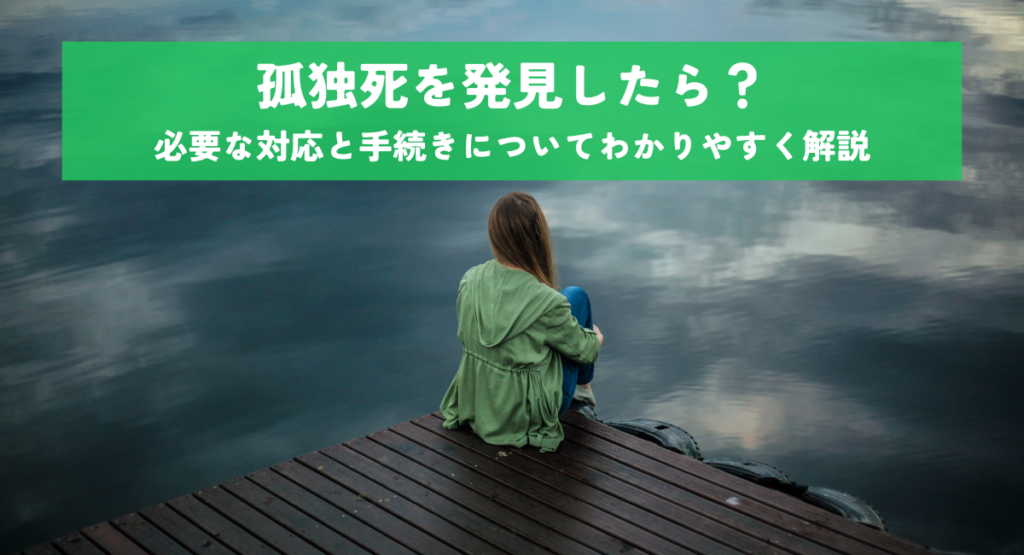一人暮らしの高齢化が進む現代社会において、孤独死は決して他人事ではありません。
異臭や不審な状況から発見されるケースも多く、発見者にとって大きな衝撃と、その後どうすれば良いのかという不安が押し寄せます。
大切なのは、冷静に状況を把握し、適切な対応をとることです。
そこで、この記事では、孤独死を発見した場合の具体的な対応、その後に行うべき手続き、そして将来的な孤独死予防のための対策を解説します。
孤独死を発見した場合の対応
発見時の状況確認
まず、発見時の状況を冷静に確認することが重要です。
ご遺体が発見された場所(例えば、寝室、リビング、浴室など)、状態(仰向けかうつ伏せか、体位、衣服の状況など)、周囲の様子(異臭の有無、その種類・強さ、窓やドアの状況、鍵のかかり具合、照明の状況、室温など)を詳細にメモしておきましょう。
スマートフォンで写真や動画を撮影することも有効です。
写真は遺体の全体像、そして特に重要な箇所(例えば、怪我や異様な痕跡など)を複数枚撮影しましょう。
動画は周囲の状況を記録するのに役立ちます。
これは後の警察への説明や手続きに役立ち、特に、死因が自然死なのか、事件性があるのか、自殺の可能性があるのかを判断する上で重要な情報となります。
例えば、遺体が不自然な体勢で発見された場合、事件性や自殺の可能性を考慮する必要があるでしょう。
もし、ご遺体が発見された場所がご自身の所有物ではない場合、例えば、賃貸マンションであれば大家さんや管理会社、親戚宅であれば所有者への連絡も迅速に行う必要があります。
警察への通報方法
ご遺体が明らかに死亡している場合、または死亡しているかどうかわからないが、明らかに異変を感じた場合は、すぐに110番通報を行いましょう。
警察に通報する際には、「〇〇市〇〇町〇〇番地にて、高齢者のAさんと連絡が取れず、自宅を訪れたところ、室内から異臭がしており、人が倒れているように見えます。
」といったように、発見場所、状況、ご遺体の状態などを落ち着いて正確に説明します。
通報後、警察官が到着するまで、現場をそのままの状態に保ち、余計なものを触らないように注意しましょう。
これは、捜査の妨げになる可能性があり、例えば、遺体の位置を変えたり、証拠となりうるものを移動させたりすると、捜査に支障をきたす可能性があります。
警察官の指示に従い、現場を離れるよう指示された場合は素直に従い、質問には正確に答えましょう。
救急隊への要請判断
ご遺体が動かず、呼吸や脈拍がないかどうかわからない場合、救急車を呼ぶべきかどうか迷うかもしれません。
しかし、少しでも生命の兆候があれば、すぐに119番に通報し、救急隊の到着を待ちましょう。
「呼吸が浅く、脈拍が弱いです」など、観察した状況を詳しく伝えましょう。
救急隊員は、生死の確認、応急処置、必要であれば病院への搬送を行います。
もし、明らかに死亡している場合は、例えば、死後硬直が確認できるなど、明らかに死亡している場合は、救急隊ではなく警察への通報が優先されます。
判断に迷う場合は、まずは119番に電話し、状況を説明して指示を仰ぎましょう。
電話オペレーターは状況を判断し、適切な機関への連絡を指示してくれます。
自身の安全確保
孤独死を発見した現場は、危険な状況である可能性があります。
ガス漏れや火災の危険性、感染症(例えば、インフルエンザや肺炎など)の危険性、鋭利な物による怪我のリスクなどを考慮し、自身の安全を確保することが最優先です。
換気を十分に行い、できれば窓を開けて空気の入れ替えを行い、必要であればマスク(できればN95マスクなど、飛沫を遮断できるもの)を着用しましょう。
一人で現場に立ち入らず、信頼できる友人や家族など複数人で対応することをお勧めします。
もし、危険を感じたら、例えば、ガス臭が強い場合や、火災の危険性がある場合など、すぐに警察や消防に連絡し、専門家の指示に従ってください。

孤独死後の手続きの流れ
遺体の状況確認
警察官が到着し、現場検証が行われた後、遺体の状況について確認を行います。
身元の確認(身分証明書や所持品から)、死亡推定時刻(状況や死後変化から推定)、死因(外傷の有無、病歴などから推定)などが警察から伝えられます。
この段階で、遺族の有無や連絡先などの情報も収集されます。
身元が不明な場合は、指紋照合やDNA鑑定などの方法で身元確認が行われるため、時間がかかる場合があります。
警察は、死因究明のため、検視を行う場合があります。
警察・検察への対応
警察による捜査の結果、事件性がないと判断された場合は、検視・解剖が行われる場合があります。
これは、死因を明確にするために行われます。
検察の判断に基づき、解剖が必要な場合もあります。
警察や検察の指示に従い、必要な書類を提出するなど、必要な手続きを進めましょう。
この手続きは、遺族にとって負担の大きいものとなる可能性がありますが、警察や検察の担当者から丁寧に説明を受けるよう努め、冷静に対処することが重要です。
例えば、検案書や検視調書などの書類を受け取る必要があります。
葬儀社の選定
遺族が決定した場合、葬儀社を選定する必要があります。
見積もりを取り、費用(葬儀費用、火葬費用、霊柩車費用など)、サービス内容(通夜・告別式の内容、お布施の金額、返礼品の準備など)、対応の良さなどを比較検討しましょう。
孤独死の場合、遺体の状態によっては特殊な対応(防腐処理など)が必要となる場合もあり、葬儀社選びは慎重に行う必要があります。
葬儀社によっては、遺品整理や特殊清掃などのサービスも提供している場合がありますので、事前に確認しましょう。
火葬・埋葬の手続き
葬儀後、火葬・埋葬の手続きを行います。
火葬場の手配(宗教・宗派による違いなど)、埋葬場所の決定(墓地、納骨堂など)、埋葬方法(土葬、火葬など)など、必要な手続きを葬儀社と協力して進めましょう。
遺族がいない場合や、遺族が引き取りを拒否する場合には、自治体が火葬・埋葬の手続きを行います。
自治体によって手続きが異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
孤独死に関する死後手続き
遺品整理の進め方
遺品整理は、ご遺族にとって精神的に負担の大きい作業です。
ご遺族だけで行うのが困難な場合は、遺品整理会社に依頼することも検討しましょう。
会社に依頼する場合は、事前に見積もりを取り、費用(作業内容、作業時間、廃棄物の処理費用など)、サービス内容(遺品の仕分け、買取、処分など)、対応の良さなどを検討することが大切です。
遺品の中には、現金や貴重品、重要な書類などがある場合もありますので、注意が必要です。
特殊清掃の依頼方法
孤独死の場合、発見が遅れると、遺体の腐敗により室内が著しく汚染される可能性があります。
このような場合は、特殊清掃会社に依頼する必要があります。
特殊清掃会社には、汚物や体液の清掃、消臭(オゾン脱臭など)、除菌、害虫駆除などを行う専門会社です。
費用は、汚染の程度(広さ、汚れの度合いなど)、作業内容によって大きく変動しますので、事前に見積もりを取ることが重要です。
特殊清掃は、専門知識と技術が必要な作業です。
相続手続きの概要
孤独死の場合、相続手続きも必要となります。
相続財産の調査(預貯金、不動産、有価証券など)、相続人の確定(戸籍謄本などが必要)、遺産分割(協議による分割、裁判による分割など)、相続税の申告など、複雑な手続きが伴います。
弁護士や税理士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続手続きには、期限があるので、早めの対応が重要です。
例えば、相続放棄の期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。
住民票の異動手続き
亡くなった方の住民票を異動する手続きも必要です。
手続きに必要な書類(死亡届、戸籍謄本など)、方法については、市区町村役所に問い合わせて確認しましょう。
手続きは、死亡届を提出することで行われます。
孤独死を防ぐための対策
定期的な安否確認
一人暮らしの高齢者の方には、定期的な安否確認が重要です。
家族や近隣住民、地域包括支援センター、民生委員、ケアマネージャーなどが協力して、安否確認を行う体制を整えましょう。
具体的な方法としては、電話連絡、訪問、手紙のやり取りなどがあります。
定期的な連絡だけでなく、様子がおかしいと感じた際には、すぐに連絡を取り合うことが大切です。
地域との繋がり
地域との繋がりを持つことは、孤独死予防に効果的です。
地域活動への参加(ボランティア活動、趣味のサークルなど)、近隣住民との交流(挨拶、簡単な会話など)などを積極的に行うことで、孤立を防ぎ、助けが必要な時に迅速な支援を受けられる体制を作ることができます。
地域のコミュニティセンターや公民館などを活用することも有効です。
生活支援サービス
高齢者向けに提供されている生活支援サービスを利用することも有効です。
食事の配達サービス(宅配弁当など)、買い物代行サービス、家事援助サービス、訪問介護サービスなど、さまざまなサービスがあります。
自治体の高齢者支援窓口や地域包括支援センターに相談することで、適切なサービスを紹介してもらえます。
心の健康相談窓口
心の健康に不安がある場合は、専門機関に相談しましょう。
相談窓口は、地域によって異なりますが、多くの地域で保健所、精神科病院、地域包括支援センターなど、相談窓口が設置されています。
匿名で相談できる窓口もありますので、気軽に相談してみましょう。
まとめ
孤独死を発見した場合、まずは冷静に状況を把握し、警察や救急隊への通報を適切に行うことが重要です。
その後は、警察・検察への対応、葬儀社の手配、火葬・埋葬の手続きなど、さまざまな手続きを進める必要があります。
遺品整理や特殊清掃、相続手続きなども必要となる場合があり、ご遺族には大きな負担がかかります。
孤独死を防ぐためには、定期的な安否確認、地域との繋がり、生活支援サービスの利用、心の健康相談窓口の活用などが有効です。
一人ひとりが、孤独死問題に関心を持ち、予防に努めることが大切です。